布薩(ふさつ)
かれこれ三年になろうかと思いますが、
毎月二回布薩を僧堂で行っています。
これがどういう儀式なのか、
具体的にどういうことをしているのか、
どんな意義があるのかなど詳細については、
「彼岸寺」で紹介してくださっていますので、そちらをご覧ください。
懺悔礼拝(さんげ らいはい)をひたすら繰り返し、
仏陀の定められた戒の条項をお互いに読み上げて、
自ら反省し、これからも戒にもとる行いがないように心に誓うのです。
戒は、サンスクリット語の「シーラ」で、習慣、よき習慣です。
よき習慣といっても、もちろん戒を守ることに超したことはありませんが、
お互いはどうしても戒に背いてしまいがちです。
そこで、戒を意識して、戒に戻るようにすることを習慣にしようと私は申し上げています。
僧堂に暮らしていますと、実際にはそれほど戒にもとる行いがないように思われるかもしれません。
むやみに生き物を殺すこともなく、人の物を盗みとることもなく、男女の道を誤ることもないでしょう。
しかし、もっと深く見てゆけば、気がつかないうちに、小さな虫を踏み殺していることがないとはいえません。
坂村真民先生に「とげ」という詩があります。
刺さっていたのは
虫メガネで見ねば
わからないほどの
とげであった
そのとげをみながら思った
わたしたちはもっともっと
痛いとげを
人の心に刺し込んだりしては
いないだろうかと
こんな小さいとげでも
夜なかに目を覚ますほど痛いのに
とれないとげのような言葉を
口走ったりしなかったかと
教師であったわたしは
特にそのことが思われた
(『坂村真民全詩集第三巻より』)
こういう詩の心が大切です。
いくら人を傷つけないように気をつけていても、
知らぬうちに傷つけてしまっていることがないとは言い切れません。
とても戒を十分には守れていないのではないか、
知らないうちに誰かに辛い思いをさせていたのではないか、
申し訳ないなと、心に恥じ入ることが大切です。
これが「懺悔」の心なのです。
戒を意識することは、「懺悔」の心をつちかってくれるものです。
横田南嶺
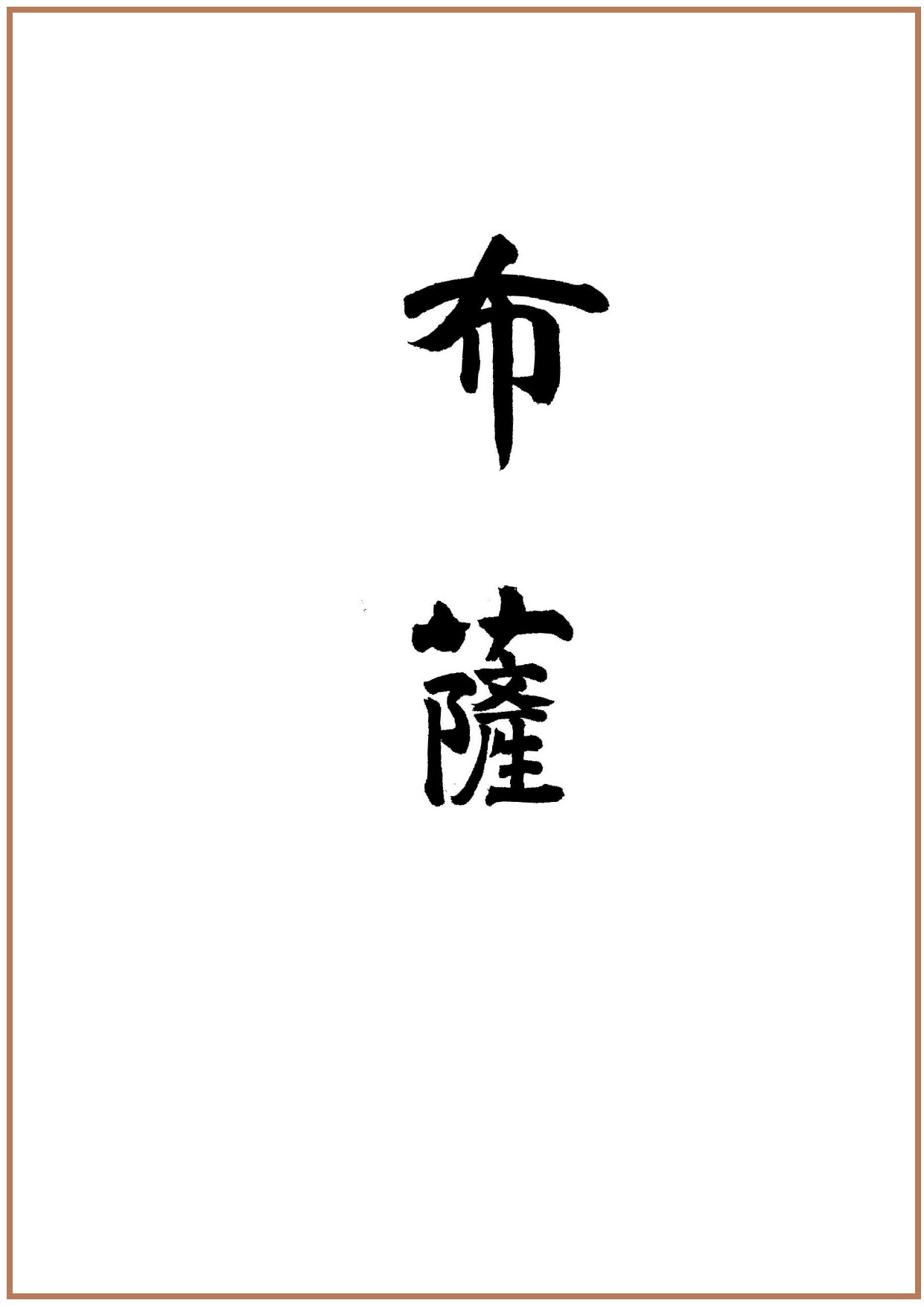
(僧堂で作成し使用している「布薩講本」表紙)

(「布薩講本」15頁より)

