「山 また 山」
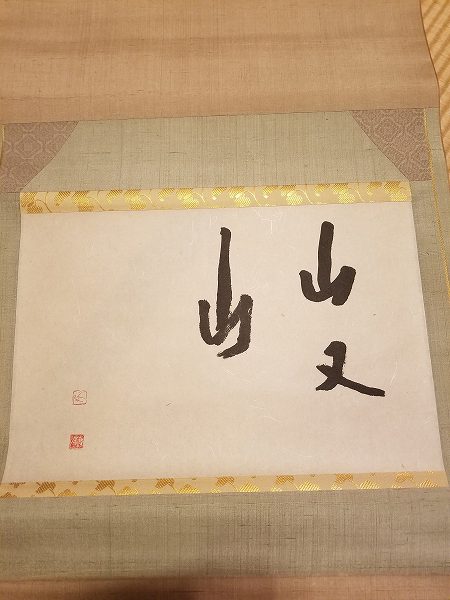
森信三先生の直筆。
昔、斉の孟嘗君(もうしょうくん)が秦の王に幽閉され、どうにか脱出して函谷関の関所までたどり着きました。
関所の決まりでは、朝に鶏が鳴いて初めて旅人を通すようになっていました。
孟嘗君は秦王が追ってくることを恐れていました。
そこで、仲間に鶏の鳴きまねが上手な者がいたので、彼に鶏の鳴きまねをさせると、関所の鶏たちが一斉に鳴き出しました。
それで関所が開いて、孟嘗君は無事通りぬけることができました。
函谷関の関所は、鶏の鳴きまねで通れたかもしれませんが、
禅の関門関所はそんなマネでは通りません。
禅の関所は、とりもなおさず公案であります。
公案は、ごまかしでは通りません。
どうにか一つ通ったと思っても、その先にまた関所があります。
山を越えたと思っても、また更に山があるようなものです。
山また山をひたすら越えてゆく修行であります。
すこしばかり公案が透って、これでいいと思うような心を慢心と言います。増上慢とも申します。
少々のことで満足することなく、まだまだと、山また山を越えてゆく覚悟で、
自らの怠惰な心や慢心に自ら警策を打って進んで欲しいものです。
(平成31年1月 横田南嶺老師 制末大攝心提唱より)

