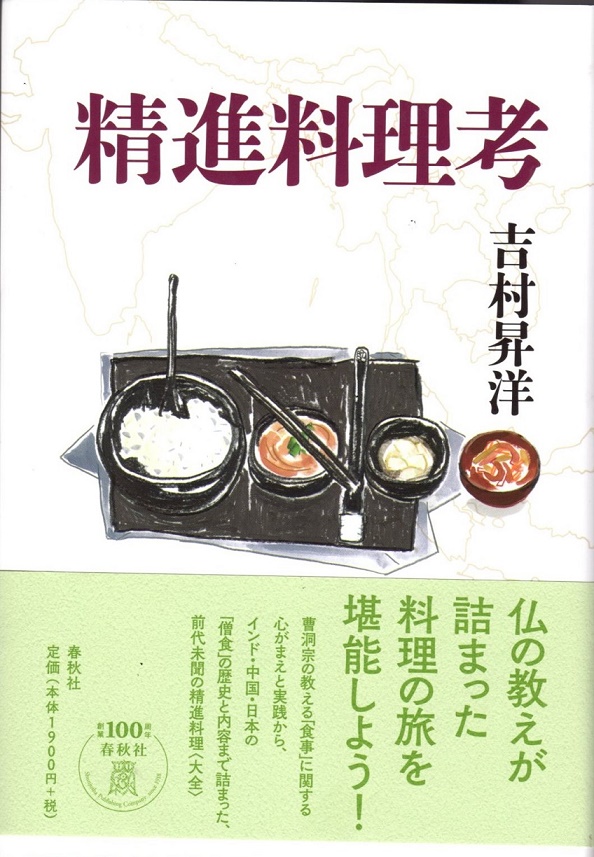五事をととのえる
世田谷区野沢の龍雲寺の
細川晋輔老師から、本が送られてきました。
細川老師は、お若いながらも
修行もできて、学識も深く、
それでいて何事においても意欲的であり、
普段から懇意にさせてもらっています。
私も、今臨済宗ではもっともその将来を
期待する禅僧であります。
その細川老師から本が送られてきたので
てっきりご自身の新著かと思いきや、
曹洞宗の吉村昇洋和尚の新著
『精進料理考』という本でした。
なんでも細川老師がお読みになって
良かったと思われたそうなのです。
吉村和尚のことはよく存じ上げませんが、
せっかく頂戴した本ですので、
じっくり読んでみようと思っています。
目次を見て、パラパラと中を開いてみていると
こんな言葉が目に入ってきました。
「咀嚼中は箸を置く」
という一語です。
吉村和尚は、
「ひとつの料理を口に運んだら
咀嚼中は必ず一度箸を置き
手は膝の上で法界定印(ほっかいじょういん、
坐禅中の手の組み方で、手のひらを上に向けて
右の手の上に左手をのせ、親指で輪を作る形)を組む。
そして、口の中が空っぽになったら、再び両手で箸を取り
器を持って食事を再開していく」と
書かれていました。
私など、長年僧堂にいますので
知らず知らずのうちに、早く食べる習慣が
身についてしまいました。
早く食べて飲み込んでしまうのは
胃腸にもよくありません。
どうして、臨済宗の僧堂では早く食べるようになったのか
不思議に思います。
やはりゆっくりと咀嚼していただいた方がいいと思い、
その日の晩から、お料理を口に入れたら
箸を置いて、法界定印を組んで
咀嚼するようにしていますが、
果たしていつまで続くことやら…
天台大師は、五事を調えることを説かれています。
それは
調五事
調食=適度な食事をとること
調眠=適度な睡眠をとること
調身=身体を調えること
調息=呼吸を調えること
調心=心を調えること
我々禅では、身体と呼吸と心を調えることを
説いていますが、
その前提となるのが、食を調え、睡眠を調えることです。
これが土台となって、その上で身体と呼吸と心を調えるのです。
ですから、食事を調えるということは
大切なのことなのです。
吉村和尚は、この食について実に
270ページに及ぶ著書を出されました。
私も知らないことが多く、内容が実に豊富であります。
私にわざわざ贈呈してくださった細川老師の
お心もありがたくいただいて、
読んでいるところであります。
おすすめです。
横田南嶺